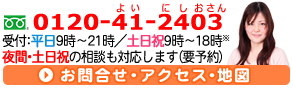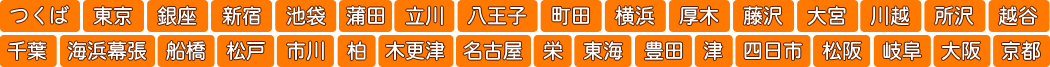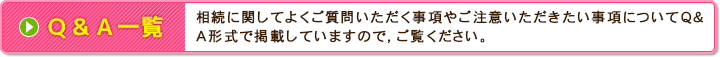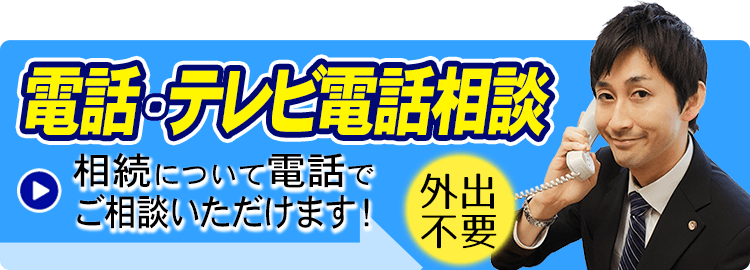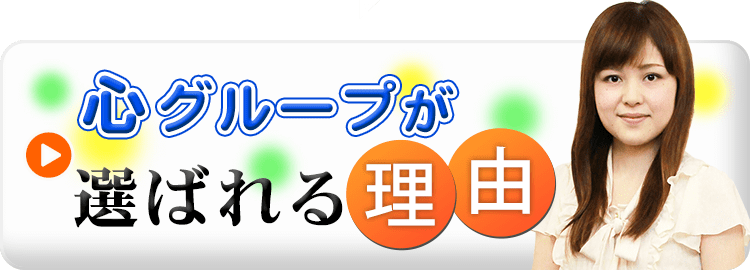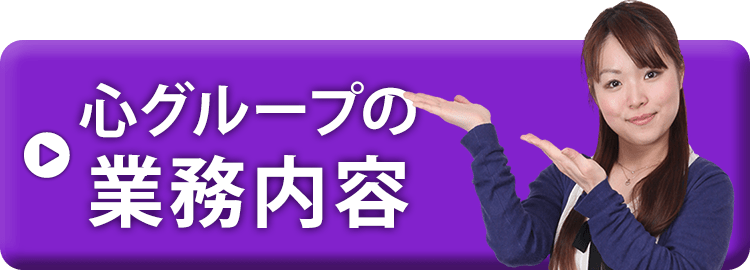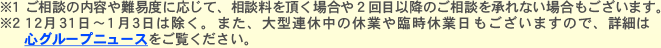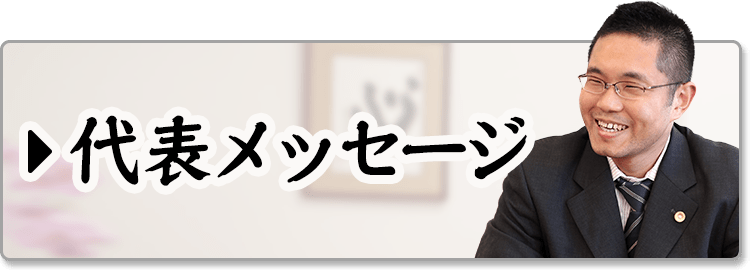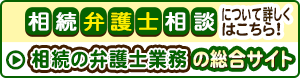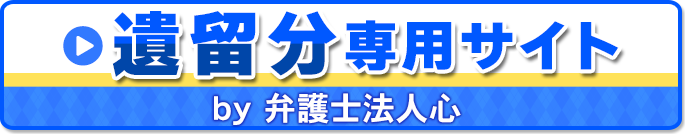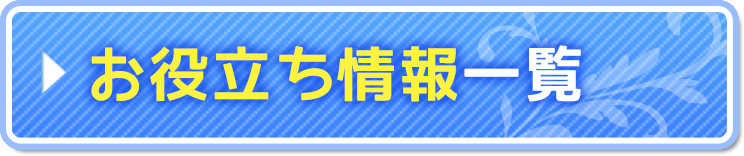不動産の共有名義人が亡くなった場合の相続手続きの方法
1 不動産の共有持分の相続
不動産の共有名義人がお亡くなりになられた場合には、その共有名義人が持っている不動産の共有持分だけが相続の対象となります。
そのため、当該共有持分のみについて、遺言がある場合には遺言に従い、遺言がない場合には遺産分割協議を行い、相続登記をするなどの相続手続きを進めていくことになります。
2 遺言がある場合
遺言があり、特定の相続人に不動産の共有持分を相続させる旨が記載されている場合には、基本的にはその内容のとおりに相続登記を行います。
もし遺言が自筆証書遺言であり、法務局の自筆証書遺言書保管制度を用いていない場合には、相続登記に先立って検認手続きを行う必要があります。
3 遺言がない場合
遺言がない場合には、戸籍謄本を収集して相続人を確定させたうえで、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
集めなければならない戸籍謄本は、基本的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本です。
代襲相続が発生している場合には、これらに加えて被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人が有していた不動産の共有持分を、誰が取得するかを決めます。
例えば、自宅不動産を父と母が持分2分の1ずつで共有していて、父が亡くなったというケースにおいて、相続人が母と子2人であった場合、母が父の共有持分2分の1をすべて取得するとすることで、自宅不動産は母の単独所有にすることができます。
遺産分割協議で決めた内容は協議書に記載し、相続人全員が署名と実印による押印をしたうえで印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の作成まで終わりましたら、相続登記を行います。
なお、遺言がある場合、ない場合にかかわらず、2024年4月1日より相続登記は義務化されており、正当な理由なく一定の期限内に相続登記を行わない場合には罰が科されることもありますので、注意が必要です。