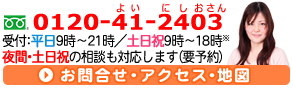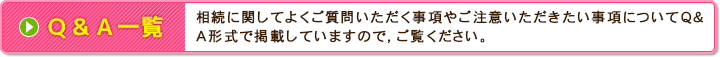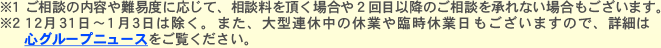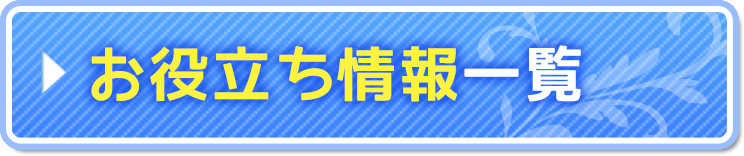遺留分を請求する際によく争われるポイント
1 遺留分の請求をお考えの方へ
特定の人に遺産が集中している、他の相続人は被相続人から生前に贈与があったのに自分は贈与されていないなどの理由で、遺留分の請求をお考えになっている方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、民法改正後、令和元年7月1日以降に相続が開始する場合において、遺留分の請求の際によく争われるポイントについてご説明いたします。
2 請求権行使の期間
⑴ 遺留分を請求できる期間と請求方法
まず、遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求権を行使するにあたり、行使期間が法律で規定されているため、その期間内に請求をする必要があります。
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は、相続開始の時から10年で、請求権は消滅してしまいます。
遺留分の請求は、口頭でも構いませんが、「言った・言わない」で争いになることがあります。
そのため、内容証明郵便(配達証明付)で侵害者に対して請求する旨を送付しておくのがよいかと思います。
⑵ 期間制限における争点
期間制限についてよく争われるのは、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」というのがいつになるかという点です。
この点については旧法下の判例で、「贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時をいう」とされています。
例えば、被相続人が、特定の相続人に遺産をすべて相続させるような内容で自筆の遺言書を作成していたような場合において、検認手続の案内があり、特に理由なく検認手続に参加せず、その後も検認済の証明書などで遺言の内容も確認しなかった相続人がいたとします。
その相続人が、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らなかったと主張し、検認手続から1年を超えて遺留分の請求をしたような場合は、請求が認められない可能性が高いため注意が必要です。
3 遺留分の算定の基礎となる財産で争われること
⑴ 特別受益にあたるか
遺留分の算定の基礎となる財産に、ある相続人が生前に被相続人から贈与を受けた財産が含まれるかという点については、令和元年の民法改正で変更がありました。
従来は、特別受益にあたる財産については、何年前になされた贈与かは関係なく、すべて遺留分算定の基礎に含まれるとされていました。
しかし、改正により、特別受益にあたる財産についても、相続開始の10年前より前の贈与であれば、遺留分算定の基礎となる財産に含まれないこととなりました。
いずれにしても、相続人に対する贈与については、それが特別受益にあたる場合に、遺留分の算定の基礎となる可能性が出てきます。
そのため、贈与が特別受益にあたるかどうかが争われることが多いです。
特別受益については、持ち戻し免除の意思表示があったと認められても、遺留分の算定の基礎には含まれるという点を除いては、判断基準などは遺産分割の際の判断と同じです。
⑵ 遺留分権利者に損害を加えることを知りながらされた贈与か
上記のとおり、相続人以外に対する贈与で相続開始前1年より前に贈与されたものと、相続人に対する特別受益にあたる贈与で相続開始前10年より前に贈与されたものについては、原則として遺留分算定の基礎には含まれないことになります。
しかし、その贈与が、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされたものであるときは、贈与の時期に関係なく、遺留分算定の基礎となる財産に含まれることになります。
そこで、原則の期間より前にされた贈与については、「遺留分権利者に損害を加えることを知って」された贈与かどうかが争われることが多いです。
「遺留分権利者に損害を加えることを知って」された贈与にあたるには、損害を加えることについての積極的な意欲や目的までは必要ではなく、遺留分権利者に損害を与えることの認識で足りるとされています。
そして、贈与当時に遺留分権利者に損害を与えることを認識していただけでは足りず、将来の相続開始時までに被相続人の財産に何らの変動もないこと、少なくともその増加のないことを予見していた事実があることを必要とするとされています。
基本的に、この点が争われる場合は、かなり昔の贈与が問題となる場合が多いと思われますが、そのような昔の贈与であれば、贈与者はすでに亡くなっているわけですので、贈与の当事者双方の内心については知ることは難しいといえます。
そこで、贈与財産の全財産に対する割合、贈与時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから将来財産が増加する可能性等を客観的に判断するしかないところですが、資料も乏しいことが想定されます。
そのため、調停で相手方を説得するのも難しいでしょうし、訴訟で立証するのも困難な場合が多いかと思います。
⑶ 財産の評価
遺留分の基礎となる財産のうち、贈与された財産の評価は、贈与時ではなく、相続開始時の時価で算定することになります。
そこで、調停では、価額が変動する株式等につき、どの時点で評価するのかが争われることがあります。
また、不動産については、評価時期だけでなく、固定資産税評価額か、相続税評価額か、不動産業者の査定額かといった評価基準について争われることも多いです。